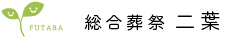よくあるご質問
-
臨終の直後にはまず何をしたらよい?
-
身近な人に連絡を取ります。菩提寺や付き合いがある教会、葬儀社などにもすみやかに連絡します。
-
病院で亡くなった場合注意することは?
-
臨終を確認した医師から「死亡診断書」を受け取ります。
この「死亡診断書」は後で火葬許可証と引換えになりますので、コピーを取っておくほうがよいでしょう。
ご遺体は処置(清拭)が済み次第、病院から引取らなければなりません。そのため、葬儀社にはすぐに連絡をして寝台車の手配をしておきましょう。
-
喪主は誰がするべき?
-
喪主は遺族の代表であり葬儀の主宰者です。一般的に故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などが務めます。
これに対して施主とは葬儀費用を負担して葬儀を運営する者を意味します。通常は喪主と施主は同一の人が務めます。
-
お寺へのお布施の相場は?
-
菩提寺か葬儀社手配かでも違いますし、地域性もあります。菩提寺の場合は詳しい親戚の年長者に尋ねたほうがよいでしょう。
弊社でお寺様をご紹介させていただく場合のお布施の目安は以下のとおりです。- 戒名が不要の場合:10万円~(葬儀・初七日・炉前読経)
- 戒名をつけて頂く場合:15万円~(葬儀・初七日・炉前読経)
-
お布施を渡すタイミングは?
-
通夜または葬儀・告別式の開式前にご挨拶に伺う際にお渡しするとスムーズです。
弔事袋に包み「御布施」の表書きと施主の名前をフルネームで記名します。菩提寺については「御布施」と「戒名料」を分ける場合がありますので確認してください。
なお、直接手渡しするのではなく切手盆や袱紗を使って渡すほうが礼儀に適っています。
-
忌日法要の数え方は?
-
初七日の数え方は関東と関西では異なります。
関東は死亡した日を入れて7日目が初七日。
関西は死亡した日の前日から数えて7日目が初七日。通常四十九日までの期間を忌中といい、四十九日法要をもって忌明けとします。以降満1年目を一周忌、満2年目を三回忌、満6年目を7回忌とします。
-
葬儀で使用する不祝儀袋の表書きは「御霊前」「御仏前」どれを使えばいい?
-
通常表書きは参列する葬儀の宗教に合わせて選びます。
仏式では「御霊前」が一般的です。ただし浄土真宗では宗旨に基づき「御仏前」を用います。
神式では「御霊前」のほかに「御玉串料」を、キリスト教式では「お花料」を用います。
-
香典を連名で渡したいときは?
-
2~3名の場合は水引の下の部分に右側が目上の人になるように順番に氏名を書きます。
4名以上の場合は代表者の氏名を表書きし左に「外一同」として、袋の中に全員の氏名を書いた紙を入れます。